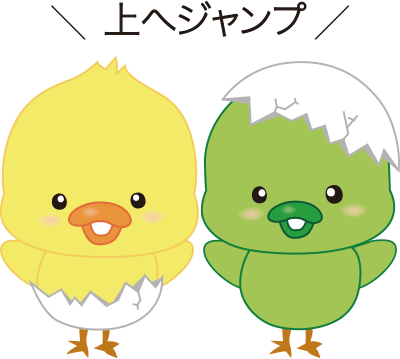お役立ち情報コラム
生活に役立つ情報や営農情報をお届けします
ライフ 2024年3月
お米をおいしく楽しもう 「ご飯」って何だろう?
 五ツ星お米マイスターの小池理雄(ただお)です。
五ツ星お米マイスターの小池理雄(ただお)です。
さて突然だけれども……。皆さん、「ご飯」って知ってますか?
「……ご、ご飯? だって毎日食べているもの。朝ご飯はパンで、昼ご飯はご飯で……」「あれ、そういえばなんでお米のことも食事のこともご飯って言うんだろう……?」と不思議に思ったことはないかな?
パンやそばのように、お米を使っていなくてもご飯と呼ぶこともありますね。
実は日本語においてご飯とは、いくつかの違う意味を持つ言葉なんだ。この言葉がお米を指す場合と食事全般を指す場合があるのだけれども、その理由には日本の歴史と文化が影響しているんだ。
日本では長い間、主食としてお米を食べてきました。まずお米があって、その周りにみそ汁があって、おかずがあって……といった風にね。そういった歴史があるからご飯といえば、お米を指したり食事全般を指したりするんだ。
そんな国、他にあるのかな? 例えば英語ではお米は「Rice」だけれども、食事は「Meal」。英語では別の意味だけど、日本人は同じ意味で使うんだ。
日本人が一人当たり一日で取るカロリーのうち、最も多いのはやはりお米。全体の20%も占めているんだ。
しかもお米は98%が国産なんだ。お米以外の穀物だと、小麦は17%、大豆は7%で、いかにお米が日本人にとってなくてはならない大事な食糧であるかが分かるね。
それなのに……。日本人が年間で食べるお米の量は、実はここ60年くらいで半分以下に(泣)。これほどまでにお米を食べなくなった理由はいろいろあるけれど、お米が身近過ぎて興味がなくなった人が多いということもあります。
でもちょっと待って! お米って本当はとても楽しいし、とてもすごい食べ物なんだ! この連載を通じてお米の楽しさやすごさ、おいしさを一緒に見ていこう!
五ツ星お米マイスター●小池理雄
なくそう食品ロス 野菜の食品ロスを減らす工夫
 家庭で最も捨てられる食品、野菜。買い方や保存方法の工夫で食品ロスを減らすことができます。
家庭で最も捨てられる食品、野菜。買い方や保存方法の工夫で食品ロスを減らすことができます。
■ 野菜の買い方
●買い物前に冷蔵庫の野菜をチェックし、買い物メモを作る
●日持ちしないニラやもやしはできるだけ使う直前に買う
●レタスやキャベツは2分の1個、4分の1個などを買う
●まとめ買いせず、1個単位で必要な分だけ買う、など 後で腐らせて駄目にするくらいなら、多少割高でも、最初から使う分だけ買うのがお勧めです。
■ 野菜の保存方法 冷蔵庫の野菜室を紙袋などで区分して、どこに何があるか分かりやすくしておきましょう。 野菜の中で特に日持ちしないのはもやしです。もやし生産者協会によれば、もやしを保存するのは野菜室より温度の低いチルド室や冷蔵室がお薦めだそうです。買ってきたら袋に穴を開ける、あるいは電子レンジにかける、水を張った容器に入れるなど、ひと手間でロスを減らせます。
ショウガや青ジソなどは、湿らせたキッチンペーパーでくるみ、青菜は市販の野菜保存袋に入れてから冷蔵すると長持ちします。
■ 干し野菜もお薦め キュウリを斜め輪切りにしてざるに並べ、半干しにして酢やしょうゆ、ごま油のたれにもみ込むと、おいしい一品になります。エノキタケやシイタケ、ダイコンもお薦めです。
■ 漬け物にしてみよう 義母に教わった、ダイコンとセロリの漬け物を紹介します。 材料は、ダイコン1本、セロリ5、6本、ニンジン少々、昆布1枚、ショウガ適量、トウガラシ5、6本。調味料は砂糖175g、しょうゆ250ml、酢100ml。 全ての材料を袋に入れ、半日置けば食べられます。裂きイカを入れるとだしの代わりになります。ナガイモも同じ調味液で漬けられました。いろんな野菜で試してみましょう。
食品ロス問題ジャーナリスト●井出留美
おいしく食べて美しく 食べ物で春の体調不良対策
 少しずつ気温が高くなり過ごしやすい季節の春になりました。しかし、だるさ、頭痛、疲労感などの体調不良を訴える方も少なくありません。原因は、気温の寒暖差、環境の変化により自律神経のバランスが乱れるためです。今回は、自律神経を整える効果が期待できるお薦めの食べ物二つをご紹介します。
少しずつ気温が高くなり過ごしやすい季節の春になりました。しかし、だるさ、頭痛、疲労感などの体調不良を訴える方も少なくありません。原因は、気温の寒暖差、環境の変化により自律神経のバランスが乱れるためです。今回は、自律神経を整える効果が期待できるお薦めの食べ物二つをご紹介します。
■ タケノコ
タケノコには、多幸感を感じるドーパミンなどの神経伝達物質を作り、自律神経を整えるために欠かせないアミノ酸の一つのチロシンが含まれています。節の間にある白い粉のようなものがチロシンです。チロシンは体内で合成されるため、不足することはないと考えられています。しかし、無理な食事制限をすると不足する恐れもあるため、3食しっかり食べるようにしましょう。バターとしょうゆで炒め、チーズをのせてトースターで焼くと煮物に飽きた方でもおいしく食べられます。
■ イチゴ
イチゴには、ストレスへの抵抗力を高める働きがあるビタミンCが含まれています。しかし、過剰に取っても余剰分は尿と一緒に排出されるため、一度に過剰に取るのは控えましょう。毎食取るのが好ましいです。ビタミンCは、コラーゲンの合成に欠かせない栄養素のため、美しい肌を保ちたい方は積極的に取るようにしましょう。イチゴに含まれるビタミンは水溶性ビタミンで、水に溶けやすく熱に弱い性質があります。生で食べるのがお薦めです。食後のデザートにイチゴを食べると良いでしょう。
自律神経を整えるためには、腸内環境を整えることも必要です。幸せホルモンと呼ばれ、自律神経のバランスを整えるために必要なセロトニンの9割は腸で作られます。今回ご紹介した食べ物の他に、腸内環境を整える働きがある、食物繊維を多く含む海藻や野菜なども取るようにしましょう。
栄養士●吉田理江
身近な草木 和ハーブ入門 ヨモギ 日本の暮らしに溶け込む万能和ハーブ
 この時期、足元で春光を浴びて一斉に芽吹いている草たちの姿が目に入ってきます。その中で、新緑の葉を1枚ちぎって、草餅のようななじみある香りがしてきたら、それはヨモギかもしれません。「よく燃える(萌〈も〉える)」「四方へ伸びる」など、その生命力が呼び名になった「ヨモギ(蓬)」は、日本の北から南まで、暮らしの身近に寄り添ってきた「和ハーブ」(※)です。
この時期、足元で春光を浴びて一斉に芽吹いている草たちの姿が目に入ってきます。その中で、新緑の葉を1枚ちぎって、草餅のようななじみある香りがしてきたら、それはヨモギかもしれません。「よく燃える(萌〈も〉える)」「四方へ伸びる」など、その生命力が呼び名になった「ヨモギ(蓬)」は、日本の北から南まで、暮らしの身近に寄り添ってきた「和ハーブ」(※)です。
平安文学の『枕草子』では、牛車の車輪に踏まれたヨモギの香りが漂ってくることは趣がある、と描写されています。清少納言にとって普段気にも留めていなかった身近な野草の存在に、ハッとした瞬間があったのでしょう。一方で『源氏物語』の蓬生(よもぎう)の帖(じょう)では、荒れ果てた屋敷にヨモギが生命力の限りに生い茂り、住む人来し人の気配がないわびしさとの対比が浮かび上がってくるようです。平安と令和、時代を飛び超えて同じヨモギに心動かされるのもまた、いとをかし(=趣がある)と感じます。
さてお話を現代に戻しましょう。春のヨモギは、あくが少なく香りも柔らかで指先で簡単に摘める若葉がおいしいところです。そのまま天ぷらでいただく他にも、塩ゆでした後に水でさらしてクルミとあえたり、刻んで餅粉と混ぜて新緑色のお団子、ジェノベーゼ風のパスタペーストにしたりと、調理方法も味もさまざまに楽しめます。食物繊維や鉄分、ビタミン類なども豊富です。香りとともに春の旬を取り込んでみたいですね。
生葉をもんだ汁は、小さな傷口の止血や虫刺され時のかゆみ止めにもなる優れものです。茎葉を乾燥させておけば、お茶にお風呂にと一年中手軽に利用できます。
※和ハーブとは、江戸時代以前より日本人の暮らしと健康を支えてきた有用植物のこと。在来種の他、外来種も含みます(一般社団法人和ハーブ協会の定義による)。
植物民俗研究家/一般社団法人和ハーブ協会副理事長 平川 美鶴 (ひらかわ みつる)