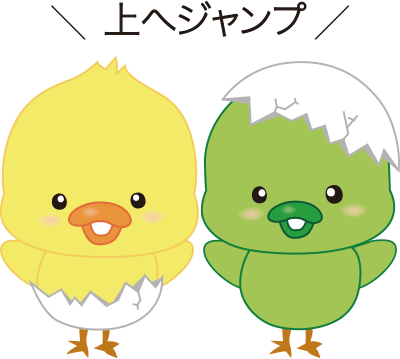お役立ち情報コラム
生活に役立つ情報や営農情報をお届けします
ライフ 2024年6月
お米をおいしく楽しもう 身近なお米をたくさん食べよう
 みんなが大好きな食べ物って、何かな?
みんなが大好きな食べ物って、何かな?
例えば、おすし。マグロ、サーモン、イクラ……。みんなの好きなものばかり。でも考えてみて。いろいろなネタがあるけれど、それらは全てお米の上にのっかっているね。
例えば大福。あんこやイチゴなどのフルーツが、もっちりして厚みのある皮に包まれているね。でも考えてみて。その皮って実はもち米というお米から作られているんだ。
他にもおせんべいなどのお菓子や、おにぎり、牛丼や親子丼といった丼飯。それら全てにお米が使われているよね。
日本には行事食といって季節ごとのイベントで食べる食事があります。例えば正月だとお雑煮、5月のこどもの日はかしわ餅、秋の十五夜ではお団子など。昔から行われてきたイベントでは必ずといっていいほどお米が登場しているね。
そう、ここまでみんなにとって身近……、身近なだけではなく好きな食べ物で使われているのがお米なんだ。
でも……。最初にみんなに話したように、今、日本人はお米を食べなくなっています。お米を食べなくなってきているということは、作られているお米の量も減ってきているということ。そして田んぼがだんだんと減ってきているんだ。田んぼは長い年月をかけて私たち日本人が作り出してきたお米を栽培する装置。
でも田んぼは自然の中にあるから、一度でも管理をやめてしまうと雑草が生えたり、土が硬くなったりしてすぐには元に戻らないんだ。
「お米を食べると太る」と言ってお米を避けている大人たちは、弁当のお米の代わりにブロッコリーを入れたり、おすしではお米の代わりにダイコンや豆腐を使ったりするけれど、お米がなくなればみんなもそういった食べ方になってしまうんだ。
そうならないように、みんなが普段の食事からお米をしっかり食べる、ということも大事なんだね。
五ツ星お米マイスター●小池理雄
小池精米店三代目店主。1971年東京・原宿生まれ。大学卒業後、出版社、人事制度コンサルティングファームなどを経て、
2006年に小池精米店を継ぐ。それまでの社会経験を生かし、新しいお米屋さんのあり方を常に模索している。
なくそう食品ロス 干し野菜で食品ロスを減らそう
 私が定期的に記事を書いている「Yahoo!ニュース エキスパート」。これまで733本の記事を執筆し、2018年には600人の書き手の中から「Yahoo!ニュース 個人アワード」を受賞しました。
私が定期的に記事を書いている「Yahoo!ニュース エキスパート」。これまで733本の記事を執筆し、2018年には600人の書き手の中から「Yahoo!ニュース 個人アワード」を受賞しました。
先日授賞式に行ったところ、パネルディスカッションに最年少の野菜ソムリエプロが登壇していました。24年3月29日で16歳になった緒方湊(おがたみなと)さんです。
緒方さんは、1歳の頃から野菜が大好き! 最年少で野菜ソムリエ資格を取得、今では農研機構の広報アンバサダーや茨城県のいばらき大使など、さまざまな役職を務めていらっしゃいます。野菜嫌いの子を持つ親御さんが聞いたらうらやましく思うでしょうね。 緒方さんがパネルディスカッションで紹介した24年のトレンドとして「干し野菜」がありました。野菜の水分量は高く、だからこそ日持ちが短く、家庭の中で最も食品ロスになりやすい食材です。野菜を干すだけでも日持ちがぐんと長くなります。
私も以前、このコラムで「キュウリの半干し」を紹介したことがありました。キュウリを斜め輪切りにしてざるに並べ、半日ほど置いておきます。程よく水分が抜けたところで塩もみし、ごま油・砂糖・酢・しょうゆなどを混ぜたタレにもみ込むと、おいしい一品になります。
冬の間は、シイタケを干していました。魚の干物を作るような3段重ねの網にシイタケを入れて、ベランダの洗濯物干しにつり下げておきます。干ししいたけは、麺料理のだしをはじめ、いろんな料理に使うことができます。
緒方さんは、自身の公式サイト「みなとの野菜大辞典」やSNS(会員制交流サイト)などで、野菜に関するさまざまな情報を発信しています。ご覧になってみてはいかがでしょうか。
食品ロス問題ジャーナリスト●井出留美(いで るみ)
株式会社office3.11代表取締役。博士(栄養学/女子栄養大学大学院)修士(農学/東京大学大学院農学生命科学研究科)
『食べものが足りない!』『SDGs時代の食べ方』『捨てないパン屋の挑戦』など著書多数。
おいしく食べて美しく おいしく食べて梅雨の体調不良対策
 梅雨の時期になると頭痛、だるさなどの不調で悩んでいませんか? 梅雨の時期の不調を「気象病」といいます。気温、気圧、湿度などの変化により、自律神経のバランスが乱れることが気象病の原因です。今回は、自律神経のバランスを整える効果が期待できる栄養素などを三つご紹介します。
梅雨の時期になると頭痛、だるさなどの不調で悩んでいませんか? 梅雨の時期の不調を「気象病」といいます。気温、気圧、湿度などの変化により、自律神経のバランスが乱れることが気象病の原因です。今回は、自律神経のバランスを整える効果が期待できる栄養素などを三つご紹介します。
■ ビタミンB6
ニンニク、肉、魚などの動物性食品に含まれるビタミンB6は、日中優位に働く交感神経の興奮を抑える働きがあります。精神を安定させる働きがある神経伝達物質のセロトニンの原料の合成に欠かせない栄養素です。ビタミンB6は、皮膚の新陳代謝を高める働きがあるため、美しい肌を目指している人は、積極的に取ると良いでしょう。ガーリックパウダーを炒め物やスープに入れると手軽にビタミンB6が取れます。
■ ビタミンD
キノコ類、しらす干し、イワシなどに含まれるビタミンDは、セロトニンの分泌を増やす働きがあります。ビタミンDは神経伝達物質の生成に関わる栄養素です。不足するとうつ病のリスクが高まります。ビタミンDは日光を浴びると体内で合成されるため、朝ベランダに出たり、散歩をすると良いでしょう。しらすをご飯の上にのせて食べたり、野菜と一緒に炒めるとおいしくビタミンDが取れます。
■ テオブロミン
チョコレートやココアなどに含まれるテオブロミンには、自律神経のバランスを整え、脳や体をリラックスさせる効果が期待できます。チョコレートやココアなどに含まれるカカオポリフェノールには、抗酸化作用があり美肌づくりには欠かせない成分です。トーストやヨーグルトにココアパウダーをかけると手軽にテオブロミンが取れます。
自律神経のバランスを整えるためには、規則正しい生活も大切です。早寝早起きを心がけましょう。
栄養士●吉田 理江(よしだ りえ)
飲食店勤務後、料理研究家のアシスタントを経て独立。栄養指導、健康・ダイエットレシピの作成やコラム執筆、セミナー講師など幅広く活動中。
薬膳アドバイザーやアンチエイジング料理プランナーなどの資格も多数取得。
お天気カレンダー 梅雨明けの形
 子どもたちの夏休みが始まる頃に、鉛色の空から青空に変わり、ギラギラと太陽が照り付ける夏がやって来ます。梅雨明けを境に劇的に天気が変化したという子どもの頃の記憶があります。
子どもたちの夏休みが始まる頃に、鉛色の空から青空に変わり、ギラギラと太陽が照り付ける夏がやって来ます。梅雨明けを境に劇的に天気が変化したという子どもの頃の記憶があります。
例年、7月後半には各地方で梅雨明けとなります。太平洋高気圧が南から強まり、梅雨前線が北へ押し上げられる形で南から梅雨が明けると、劇的に天気が変化することが多いです。
梅雨前線が弱まり、消滅して梅雨明けすることもあります。梅雨前線が南に下がって梅雨が明けることもあります。この場合、夏の高気圧に覆われていませんが、形にはこだわらず、晴天が続くことで梅雨明けとなります。梅雨前線が消滅する形や南へ下がる形は、徐々に青空が広がり、日に日にじわじわと暑くなっていくイメージです。
近年は、暑い晴天が続いたと思ったら何日も梅雨空が戻るなど、梅雨明けを特定しにくい年も少なくありません。
気象予報士・防災士 檜山 靖洋(ひやま やすひろ) 1973年横浜市生まれ。
明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。
1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。 2005年からNHKの気象キャスターに。
朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。