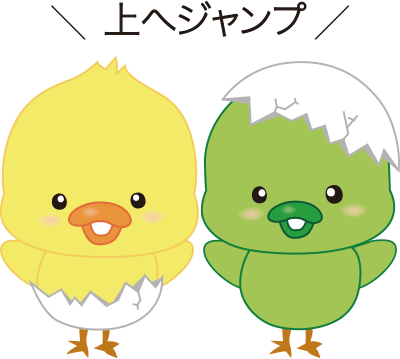お役立ち情報コラム
生活に役立つ情報や営農情報をお届けします
ライフ 2024年8月
お米をおいしく楽しもう お米作りにはどんな作業があるの?
 お米を作るには、まず種まきから始めるよ。なんと1粒のお米から400~500粒ものお米ができるんだ。茶わん1杯はおよそ3250粒なので、種が7粒もあれば十分にご飯1杯分になるね。
お米を作るには、まず種まきから始めるよ。なんと1粒のお米から400~500粒ものお米ができるんだ。茶わん1杯はおよそ3250粒なので、種が7粒もあれば十分にご飯1杯分になるね。
では、農家さんはどのようにお米を作っているのかな? 主な作業を一緒に見ていこう。
①苗作り……種から葉が出て、7、8cmほどに育ったものを「苗」というよ。さらに14、15cmほどになったら田植えをするんだ。ここまで育てば稲作の半分は終わったようなもの、ということから「苗半作」という言葉が生まれたよ。
②田植え……昔は手作業だったけれども今は田植え機を使うよ。機械のおかげで田植えにかかる時間は昔と比べて10分の1程度で済むんだ。
③肥料……稲が元気に育つための「稲のご飯」。田植えの前に田んぼに入れているよ。そして農家さんは「あまり元気がなさそうだな」と思ったら、また肥料を与えるんだ。
④中干し……稲の根が腐らないように、田んぼから水をなくしてカラカラに乾かすんだ。そうすると稲の根っこが健康になるんだよ。
⑤雑草取り……稲にとって雑草は大敵だ。稲のご飯を食べられてしまうからね。雑草を取るのに農薬を使ったり、アイガモという鳥に食べてもらったり、除草機という機械を田んぼに入れたりしているよ。
⑥水管理……稲が暑さに負けないよう、田んぼの水を深くしたり、ずーっと流しっ放しにしたりするんだ。まさに田んぼは「稲のプール」だね!
⑦稲刈り……農家さんは稲を見ればいつ刈り取ればいいのか分かるんだ。そこが農家さんの腕の見せどころなんだね。
こういった作業だけではなく、まだまだ細かい仕事はたくさんあるよ。稲作は「八十八」の作業があるから「米」と書く、といわれているけど、実際はとてもその程度では収まらないんだ。
五ツ星お米マイスター●小池理雄
小池精米店三代目店主。1971年東京・原宿生まれ。大学卒業後、出版社、人事制度コンサルティングファームなどを経て、
2006年に小池精米店を継ぐ。それまでの社会経験を生かし、新しいお米屋さんのあり方を常に模索している。
なくそう食品ロス 干し野菜を作ってみよう
 キュウリやナスが旬ですね。キュウリはあっという間に大きくなってしまうので、すぐ取らなければなりませんが、あまりに量が多いと食べるのが間に合いません。
キュウリやナスが旬ですね。キュウリはあっという間に大きくなってしまうので、すぐ取らなければなりませんが、あまりに量が多いと食べるのが間に合いません。
そこで便利なのがキュウリの半干しです。以前にもこのコラムで紹介しましたが、長野県で米や野菜を作っている義父母に教えたところ、おいしいと喜ばれたので、あらためてお伝えします。料理研究家の有元葉子さんの著書『「使いきる。」レシピ』(講談社)で紹介されています。
キュウリを斜め輪切りにし、ざるなどに並べて庭先やベランダに干しておきます。カラカラになるまで乾かすのではなく、触るとシナッとした感じの半干しです。私は斜め輪切りにしていますが、普通の輪切りや拍子木切りでもOKです。
半干ししたキュウリを塩もみし、ごま油や砂糖、しょうゆ、酢などであえると一品になり、お酒のつまみにもぴったり。半干しにすると、生で食べるよりさらにかみ応えが増します。私は和風だれで漬けますが、コチュジャンを使って韓国風、オリーブ油やバルサミコ酢を使ってイタリアン風などにアレンジもできるでしょう。
キュウリは生のまま食べてもいいですし、肉と一緒に炒めるのもいいですね。有元葉子さんは玄米カレーの具材としてもお薦めしています。
野菜を干す方法はキュウリ以外にも使えます。冬に旬を迎えるダイコンは切り干し大根にできます。先日、冬の間に作っておいた切り干し大根を水で戻し、絞って甘酢漬けにしたら、歯応えのあるサラダになりました。切り干し大根は、煮ると軟らかくなりますが、水で戻すとコリコリしておいしいです。
冬ならジャガイモ、秋ならキノコ、夏ならズッキーニなど応用可能です。エノキタケは干すとみそ汁の具やだしとして使えます。野菜がたっぷり手に入ったら干し野菜を作ってみませんか。
食品ロス問題ジャーナリスト●井出留美(いで るみ)
株式会社office3.11代表取締役。博士(栄養学/女子栄養大学大学院)修士(農学/東京大学大学院農学生命科学研究科)
『食べものが足りない!』『SDGs時代の食べ方』『捨てないパン屋の挑戦』など著書多数。
おいしく食べて美しく 残暑の時期の胃腸トラブル対策で美しく
 残暑の続くこの時期は、「寝ても疲れが取れない」「常に体がだるい」など日常的に疲労を感じていませんか? もしかしたら、食事が原因かもしれません。疲労回復と美肌づくりにお薦めの栄養素を二つお伝えします。
残暑の続くこの時期は、「寝ても疲れが取れない」「常に体がだるい」など日常的に疲労を感じていませんか? もしかしたら、食事が原因かもしれません。疲労回復と美肌づくりにお薦めの栄養素を二つお伝えします。
■ タウリン
イカ、タコなどに含まれるタウリンには、疲労回復効果が期待できます。タウリンはアミノ酸の一種で細胞を正常に保つ働きがあるため、体の状態を良好に保つために必要な成分です。胆汁酸の合成や分泌を促進し、肝臓の健康をサポートします。肝臓は代謝や解毒などさまざまな機能を担っている臓器です。肝機能が低下すると体の疲労につながるため、肝臓に負担をかける、食べ過ぎ、アルコールの過剰摂取に気を付けましょう。肝臓に負担がかからない食生活を心がけることが大切です。暑い日は、冷製パスタにタコ、トマトを加えるとおいしく、そして手軽にタウリンが取れます。
■ ビタミンB1
豚肉、そば、玄米などに含まれるビタミンB1は、炭水化物に含まれる糖質をエネルギーに変えるために必要な栄養素です。エネルギーの代謝が活発になれば体の機能も高まり、疲労回復に役立ちます。不足すると疲労物質の乳酸が体内に蓄積されるだけではなく、イライラしやすくなったり、食欲が低下しやすくなることがあるため、意識してビタミンB1を取るようにしましょう。タマネギ、ニラなどのネギ類に含まれるアリシンがビタミンB1の吸収を高めてくれるため、豚肉と一緒に炒めて食べると良いでしょう。そうめんの代わりにそばを食べるとビタミンB1を効率良く取れます。
暑い日は喉越しが良い麺類ばかりになりがちですが、栄養のバランスが偏り疲労が蓄積されやすくなります。野菜やタンパク質も取るようにしましょう。バランス良く食べることは、美肌づくりにも役立ちます。
栄養士●吉田 理江(よしだ りえ)
飲食店勤務後、料理研究家のアシスタントを経て独立。栄養指導、健康・ダイエットレシピの作成やコラム執筆、セミナー講師など幅広く活動中。
薬膳アドバイザーやアンチエイジング料理プランナーなどの資格も多数取得。
お天気カレンダー 「お好きな服は」
 春の七草は、栄養不足を補うために葉や茎をおかゆにして食べることが知られています。一方、秋の七草は、秋の風情を楽しむためのもので、主に観賞用です。秋の七草は、オミナエシ、ススキ、キキョウ、ナデシコ、フジバカマ、クズ、ハギです。頭文字を取って、「お好きな服は」と覚えましょう。
春の七草は、栄養不足を補うために葉や茎をおかゆにして食べることが知られています。一方、秋の七草は、秋の風情を楽しむためのもので、主に観賞用です。秋の七草は、オミナエシ、ススキ、キキョウ、ナデシコ、フジバカマ、クズ、ハギです。頭文字を取って、「お好きな服は」と覚えましょう。
秋の七草は、時代とともに変化し、一時期はヒガンバナ、ハゲイトウ、コスモス、シュウカイドウ、オシロイバナ、キク、イヌタデが選ばれたことがあります。皆さんなら、秋の観賞用にどのような七草を選びますか?
この時期は、朝晩は冷えても、日中は暑いこともあります。また、日々の気温の変化も大きくなります。朝の気象情報で、今日は「お好きな服で」とは言いづらいです。毎日の気象情報を見て、服装を合わせるようにしてください。
気象予報士・防災士 檜山 靖洋(ひやま やすひろ) 1973年横浜市生まれ。
明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。
1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。 2005年からNHKの気象キャスターに。
朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。