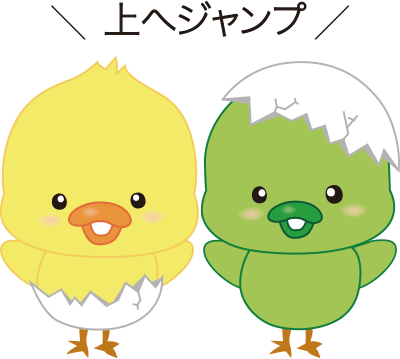お役立ち情報コラム
生活に役立つ情報や営農情報をお届けします
ライフ 2024年9月
お米をおいしく楽しもう お米がみんなの食卓に並ぶまで
 前回はお米の作り方について稲刈りまでを簡単に紹介したけれど、今回はみんなの食卓にお米が並ぶまでを見てみよう。
前回はお米の作り方について稲刈りまでを簡単に紹介したけれど、今回はみんなの食卓にお米が並ぶまでを見てみよう。
刈り取り直前の稲は、茎の先に米粒(もみ)がびっしりと付いた穂が垂れているんだ。田んぼから稲を茎ごと刈り取り、同時に穂からもみを取り外します(脱穀)。実はこの作業、昔は別々に行っていたから時間がかかったんだけれども、今ではコンバインという機械で同時に行ってしまうんだ。
お米は農産物なので、収穫直後は水分をたっぷり含んでいます。このままだとカビが生えてくるので、まずはもみを乾燥させます。乾燥により14・5~15%くらいまで水分を落とすけれども、この数字は「1年間保存ができて、かつ味も落ちない」というギリギリのところなんだ。
乾燥の後、もみを覆っている硬い殻(もみ殻)を取り外すと、中から茶色い光沢のあるお米(玄米)が出てきます。玄米は温度管理された倉庫で保管された後、トラックなどで精米所に運ばれていくんだ。
精米とは、玄米をみんなが知っている白い米粒にする作業のこと。玄米の茶色い部分(ぬか)を削るんだ。精米所は産地にも都会にもある。私のお店、小池精米店はそういった仕事をしているお店の一つなんだよ。
実は精米は難しい作業なんだ。ぬかの部分と白米の間にはお米のおいしさが詰まったうま味層がある。精米は機械で行うけれど、季節が違ったり精米するお米の品種が違ったりすると、それに合わせて機械のパワーを細かく調整してうま味層を残しているんだよ。精米と同時に田んぼから玄米と一緒に付いてきてしまった石や草の実や、割れてしまった米粒を取り除き、きれいな白米に整えてから袋に詰めるんだ。
お米がみんなの食卓に上るまでの間に、いろいろな工夫がされているのが分かるよね。
五ツ星お米マイスター●小池理雄
小池精米店三代目店主。1971年東京・原宿生まれ。大学卒業後、出版社、人事制度コンサルティングファームなどを経て、
2006年に小池精米店を継ぐ。それまでの社会経験を生かし、新しいお米屋さんのあり方を常に模索している。
なくそう食品ロス 豆腐
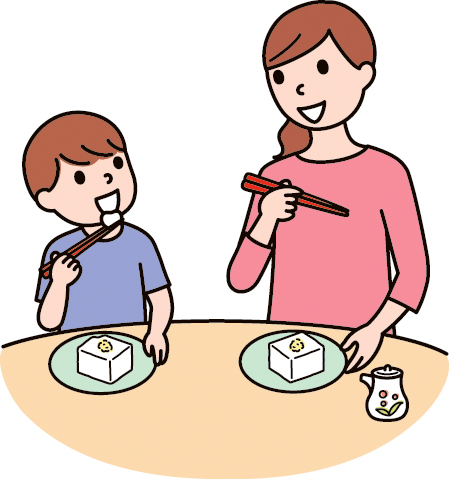 10月2日は豆腐の日。豆腐は、夏は冷ややっこ、冬は湯豆腐と一年中楽しめます。冷ややっこの薬味はショウガやネギが定番ですね。私は塩をパラっとかけ、ごま油をチラリと垂らすのも好きです。塩もごま油も質の良いものを少しだけかけるのがこつです。
10月2日は豆腐の日。豆腐は、夏は冷ややっこ、冬は湯豆腐と一年中楽しめます。冷ややっこの薬味はショウガやネギが定番ですね。私は塩をパラっとかけ、ごま油をチラリと垂らすのも好きです。塩もごま油も質の良いものを少しだけかけるのがこつです。
昔は豆腐店にボウルを持っていくと手ですくって入れてくれました。昔の豆腐は日持ちが短いですが、今では製造方法や容器包装の工夫によって15日間賞味期限がある豆腐も発売されています。
ある豆腐メーカーは、夏の冷ややっこは、前日より気温がぐんと上がったときに売れるという傾向を突き止めました。これを「とうふ指数」と名付け、売れそうな日に出荷し、そうでない日は出荷を減らしたところ、年間1000万円以上ものロスを減らすことができました。作る前に減らす(リデュース)ことが食品ロス削減においてはとても大切です。家庭でも同様で、買い過ぎ・作り過ぎを控え、適量を買って作ることが重要です。リデュースが最もお金と資源の節約になるのです。
買ってきた豆腐は、中の水が黄色く濁っている場合は密閉容器に移し替え、毎日、水を取り替えると日持ちします。冷凍すると高野豆腐(しみ豆腐)みたいな食感になります。
豆腐を作る工程でできる副産物のおからは、生のままだと日持ちしません。おから全体の生産量のうち、人間が食べているのはたった1%とのこと。残りは家畜の飼料に、もしくは産業廃棄物として捨てられています。
最近ではおからを乾燥させたおからパウダーが発売されています。きめの粗いものから細かいものまであり、用途に合わせて使えます。賞味期限が6カ月以上ある商品もあるので便利です。私は毎朝作る野菜と果物のスムージーに、きな粉と一緒に入れています。
豆腐はもちろん、おからやきな粉など大豆製品を上手に日持ちさせ、食生活に取り入れていきましょう。
食品ロス問題ジャーナリスト●井出留美(いで るみ)
株式会社office3.11代表取締役。博士(栄養学/女子栄養大学大学院)修士(農学/東京大学大学院農学生命科学研究科)
『食べものが足りない!』『SDGs時代の食べ方』『捨てないパン屋の挑戦』など著書多数。
お天気カレンダー 富士山の初冠雪
 甲府の気象台から、富士山の初冠雪が観測される日は平年10月2日です。初冠雪とは、山頂付近が雪で覆われた状態を麓の気象台から寒候期(10〜3月)に入り初めて確認できることです。山に雪が積もっても、雲に隠れて見えないと初冠雪にはなりません。晴れてきて山頂付近を確認できた日が観測日となります。
甲府の気象台から、富士山の初冠雪が観測される日は平年10月2日です。初冠雪とは、山頂付近が雪で覆われた状態を麓の気象台から寒候期(10〜3月)に入り初めて確認できることです。山に雪が積もっても、雲に隠れて見えないと初冠雪にはなりません。晴れてきて山頂付近を確認できた日が観測日となります。
富士山には一年中雪が降ります。そのため、いつがシーズン初めの雪かを判定するための条件があります。山頂の日ごとの平均気温がその年最も高くなった日を境目とし、気温が下がり始めてから初めて山の雪化粧を確認できた日が初冠雪となります。初冠雪の発表後に気温が上がり、その年の最も高い気温を上回った場合、一度発表された初冠雪は取り消され、あらためて気温が下がり始めてから観測します。2021年は9月7日に初冠雪が観測されましたが取り消され、9月26日に初冠雪となりました。一年中雪が降る富士山ならではの条件ですね。
気象予報士・防災士 檜山 靖洋(ひやま やすひろ) 1973年横浜市生まれ。
明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。
1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。 2005年からNHKの気象キャスターに。
朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。