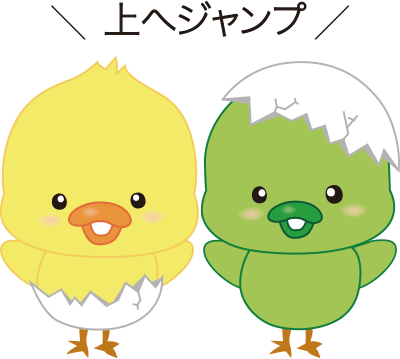お役立ち情報コラム
生活に役立つ情報や営農情報をお届けします
ライフ 2024年10月
お米をおいしく楽しもう お米のプロが教える「炊飯のこつ」
 これまでのお話で、みんなのおうちに白米(生米)が届くまでには、たくさんの人がさまざまな工夫をしていることが分かったよね。そして、みんながおいしくお米を食べるために必要な最後の工夫が「炊飯」なんだ。それまでの大勢の人の苦労を大切にするためにも上手に炊飯したいよね。
これまでのお話で、みんなのおうちに白米(生米)が届くまでには、たくさんの人がさまざまな工夫をしていることが分かったよね。そして、みんながおいしくお米を食べるために必要な最後の工夫が「炊飯」なんだ。それまでの大勢の人の苦労を大切にするためにも上手に炊飯したいよね。
炊飯は、生米のままでは堅いでんぷんを軟らかくして、人間でも消化できるようにするための調理法。だから、実は味にこだわらなければ、誰でも簡単にできることなんだよ。
でも、食べ物なんだからおいしく食べられた方が良いよね。しかもご飯は毎日食べるものだから。今回は、おいしいご飯に出合えるための外すことができない工夫を教えるから、一緒に試してみよう。 実は炊飯はどんな道具で行うかでどういった工夫をするかが変わってくるんだ。今回は電気炊飯器を使うことにして……。でも、どんな道具でも大事なのは、次の三つだよ。
①お米は優しく洗う お米は野菜や果物と一緒で農産物だから、そのまま口に入れずにまず洗うことが大事。お米の場合は汚れと共にまだ残っている「肌ぬか」を落とすことが目的だよ。
②水にしっかり漬ける でんぷんを甘くするため、そして軟らかくするために、水にしっかり漬けます。夏は1時間、冬は2時間ほど必要。簡単だけど決して省いてはいけない作業なんだ。
③炊き上がったらすぐにほぐす 炊き上がったらすぐにふたを開けて中のご飯をほぐしてね。「ほぐす」とは、しゃもじで釜の中のご飯をかき混ぜること。粒の一粒一粒に外気を当ててパリッとさせるんだ。
もちろん「炊飯のこつ」はこれだけではないけども、最低限これだけは守ればおいしいご飯にたどり着けるはず。炊飯を正しく行って初めてお米を作ってくれた人の苦労が報われるんだね。
五ツ星お米マイスター●小池理雄
小池精米店三代目店主。1971年東京・原宿生まれ。大学卒業後、出版社、人事制度コンサルティングファームなどを経て、
2006年に小池精米店を継ぐ。それまでの社会経験を生かし、新しいお米屋さんのあり方を常に模索している。
なくそう食品ロス すし
 11月1日は「寿司(すし)の日」。都落ちをした平清盛の孫、平維盛が、奈良県のすし屋で職人として身を隠し「鮨(すし)屋の弥助」と改名したのが11月1日だったとされることが由来です。
11月1日は「寿司(すし)の日」。都落ちをした平清盛の孫、平維盛が、奈良県のすし屋で職人として身を隠し「鮨(すし)屋の弥助」と改名したのが11月1日だったとされることが由来です。
日本で普及している回転ずし。数回転して客に取ってもらえなかったすしは捨てるそうです。社員やアルバイトの学生らに聞きました。
回転ずしチェーンのある企業では「出来たてをお客さまに提供したい」という思いから、回転レーンを「回さない」店舗を2012年に開店しました。注文を受けてからすしを握るようにし、食品ロスを削減しつつ売り上げを1・5倍に伸ばしました。以前は「マグロ150皿」など、売れそうな量を感覚で準備していました。しかし、注文データを翌日以降の食材準備に活用し、食材の無駄も削減できたそうです。
「食品ロスを減らすと経済が縮む」という意見を聞きます。でも、この回転ずしチェーンのように、食品ロスを減らしながら売り上げを伸ばし、食品ロス削減と経営を両立させている事例は多くあります。
そもそも回転レーンで回り続けているすしは誰のために作ったものなのでしょう? 自分がすしを作る人なら、食べてくれるかどうか分からないと作りがいがありません。作ったのに捨てられるのは切ないです。食べる側も作った人の顔が見えれば無駄に残しはしないでしょう。
私は19年から毎年、恵方巻きの売れ残り調査をしています。24年2月3日夜12時前、あるコンビニでは88本残っていました。6月にBBC(英国放送協会)の取材を受け、英語と日本語で配信されました。
私にとってすしは単なる食べ物ではなく、家族との大切な思い出でもあります。お祝いには家でちらしずしを作るのが決まりでした。
恵方巻きは貴重な食資源の結晶です。米、のり、魚介類、卵……。すしを単なる金もうけの道具にし、売れ残れば燃やして捨てればいいという、愛のない、安直な考え方は許容できないのです。
食品ロス問題ジャーナリスト●井出留美(いで るみ)
株式会社office3.11代表取締役。博士(栄養学/女子栄養大学大学院)修士(農学/東京大学大学院農学生命科学研究科)
『食べものが足りない!』『SDGs時代の食べ方』『捨てないパン屋の挑戦』など著書多数。
お天気カレンダー 気象衛星ひまわり
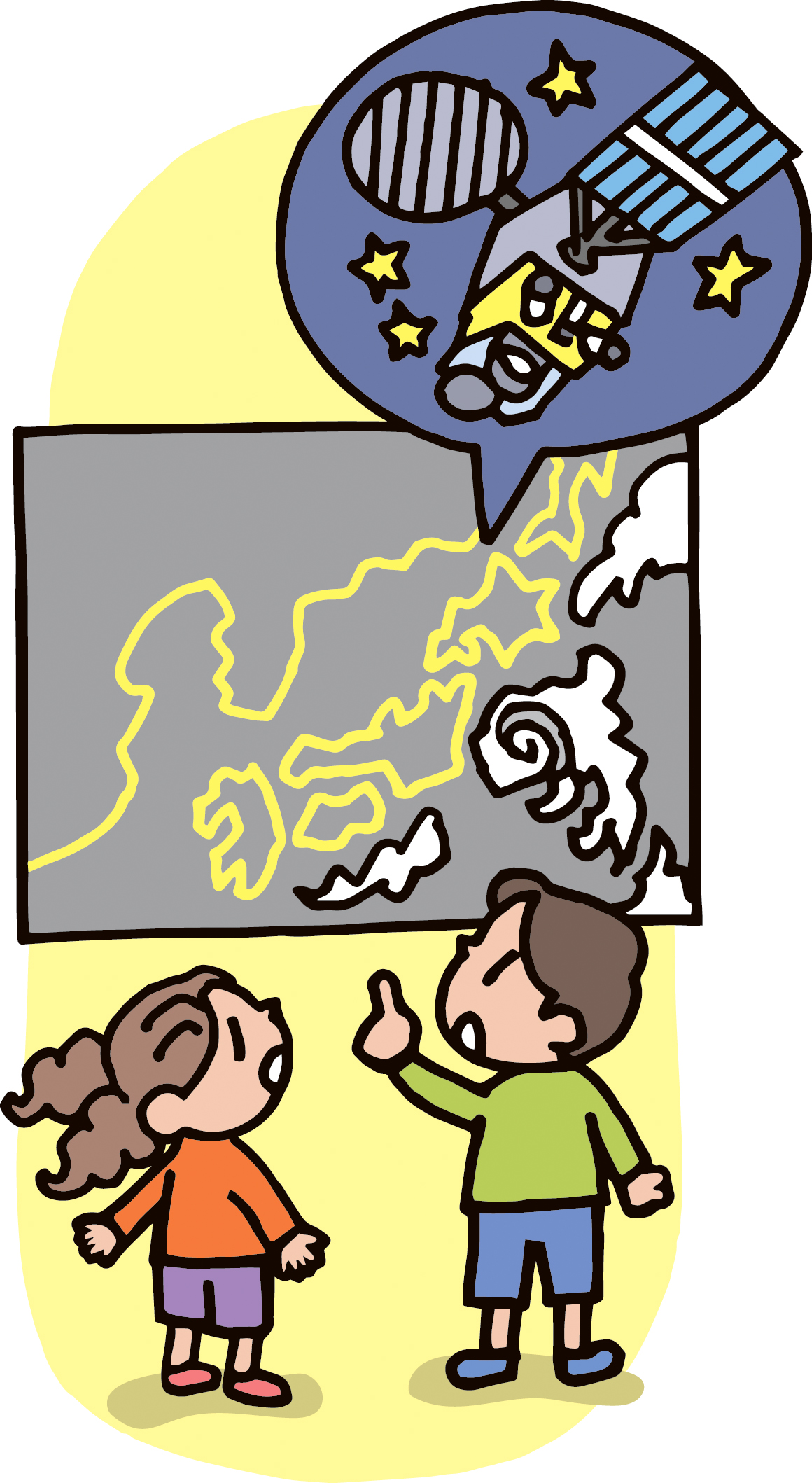 テレビやインターネット、新聞などで、気象衛星ひまわりの雲の画像を見たことがあると思います。気象衛星ひまわりは、昼間だけではなく、夜間の暗い時間でも雲の観測をすることができます。
テレビやインターネット、新聞などで、気象衛星ひまわりの雲の画像を見たことがあると思います。気象衛星ひまわりは、昼間だけではなく、夜間の暗い時間でも雲の観測をすることができます。
夜でも雲が見えるのは、赤外線を観測することで温度が分かるからです。雲のある所では、雲のてっぺんの温度が分かります。温度が低い所ほど白っぽく表示されています。温度が低い所は、上空の高い所に雲があることになります。つまり、雲画像で白くなっていれば、背の高い雲または上空の高い所に雲があるということです。逆に背の低い雲または雲がない所は温度が高く、黒っぽく表示されます。 気象衛星により観測された雲の画像を見ていると、この時期には、日本海に筋状の雲が現れ始めます。筋状の雲が現れたら、大陸から日本列島に冷たい空気が流れ込んでいる証拠です。こうなると木枯らしが吹き始めます。 。
気象予報士・防災士 檜山 靖洋(ひやま やすひろ) 1973年横浜市生まれ。
明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。
1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。 2005年からNHKの気象キャスターに。
朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。