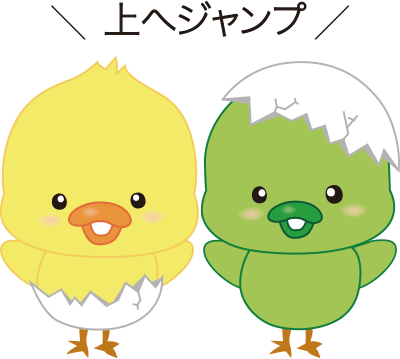お役立ち情報コラム
生活に役立つ情報や営農情報をお届けします
ライフ 2024年11月
お米をおいしく楽しもう ブレンド米
 みんな「ブレンド」って言葉を知っているかな? 簡単にいうと混ぜ物のことだね。みんなが絵の具で絵を描くときには、たくさんの色を混ぜて自分が出したい色を作るよね。それと一緒でお米も違う品種を混ぜることにより、まったく違う味が出来上がるんだ。これを「ブレンド米」というよ。
みんな「ブレンド」って言葉を知っているかな? 簡単にいうと混ぜ物のことだね。みんなが絵の具で絵を描くときには、たくさんの色を混ぜて自分が出したい色を作るよね。それと一緒でお米も違う品種を混ぜることにより、まったく違う味が出来上がるんだ。これを「ブレンド米」というよ。
ブレンド米はすごいんだ。小池精米店ではたくさんのすし店と取引があるんだけれど、その約半分は「オリジナルブレンド米」を使っているんだよ。それはすし店が作りたい理想のすしを実現するためなんだ。「お米なんて何でもいいや」ではなく、粒の大きさや、口に含んだときの粒のほぐれ具合、粘り具合など、自分の理想のすしを作るためにお米をいろいろ試した結果、ブレンド米にたどり着くんだ。
お米の味は、例えば炊き込みご飯とかまぜご飯とか、そういった料理で変わるけれど、やはり基本は「白米で食べたときの味」なんだよ。その味は品種によって違うけれど、でも新しい味を生み出すために新しい品種を作るには、実は10年単位の時間が必要なんだ。ところがブレンド米は、例えば「コシヒカリ」と「あきたこまち」を混ぜただけであっという間に出来上がる。
そう、ブレンド米は本当にすごい技術で、昔から行われていたんだ。昔は「コシヒカリ」や「あきたこまち」といったおいしいお米が少なく、手に入るお米を使っておいしく食べるためにブレンドしていたんだね。その技法が今も生きていて、精米店では新しい味を生み出す手法として使っているんだよ。
お米の味って淡泊だからあまりよく分からない……というのは海外の人たちの感想。私たち日本人はこのように繊細な味の違いを理解した上で、ブレンドによってもっと違う味を生み出しているんだ。
五ツ星お米マイスター●小池理雄
小池精米店三代目店主。1971年東京・原宿生まれ。大学卒業後、出版社、人事制度コンサルティングファームなどを経て、
2006年に小池精米店を継ぐ。それまでの社会経験を生かし、新しいお米屋さんのあり方を常に模索している。
なくそう食品ロス 卵
 お歳暮の季節が近づいてきました。最近では若い方に「オセイボって何ですか」と聞かれた話も耳にしました。
お歳暮の季節が近づいてきました。最近では若い方に「オセイボって何ですか」と聞かれた話も耳にしました。
ところでお歳暮に卵が使われたことがあるって知っていましたか?
拙著『食料危機 パンデミック、バッタ、食品ロス』(PHP新書)を執筆中に『近代日本食文化年表』(小菅桂子、雄山閣)で昔の食文化を調べました。すると、1901(明治34)年12月5日付の新聞『時事新報』で、鶏卵がお歳暮として高値が付けられたと報じられていたことが分かったのです。
『時事新報』は、福沢諭吉が1882(明治15)年に創刊した新聞です。冷蔵庫のない当時、冬場の卵は日持ちが良いのでお歳暮として重宝されており、年末近くには、卵の相場は高値になったとのこと。
前に養鶏農家を取材した際、以前は卵を常温に置いても何の問題もなかったと話していました。そこで試しに卵を常温で1年間置いてみたことがあります。1年後、一般生菌数や大腸菌群数、サルモネラ菌を調べてもらったところ、菌は検出されませんでした。大学の先生に伺うと「それは、たまたま、いい卵に当たっただけ」とのこと。中は水分が蒸発し、カラカラに乾いていましたが、すぐ腐ると思っていたので、卵の殻が中身を守る力に驚きました。
昔と違い、今は気候変動の影響で気温が高く、冷蔵することが多くなりました。殻にはサルモネラ菌が付いている恐れがあるので、パックのまま、揺れない場所(冷蔵庫の奥)に置くと良いです。すき焼きのときなどは、食べる容器に殻ごと入れがちですが、別の容器に入れることをお勧めします。
『時事新報』を創刊した福沢諭吉は卵が嫌いだったとのこと。でも卵は「完全栄養食品」といわれるほど優れた食品です
鶏は24時間以上かけて1個の卵を産みます。鶏の命と生産者の尽力に感謝して、適正価格で購入し、大切にいただきましょう。
食品ロス問題ジャーナリスト●井出留美(いで るみ)
株式会社office3.11代表取締役。博士(栄養学/女子栄養大学大学院)修士(農学/東京大学大学院農学生命科学研究科)
『食べものが足りない!』『SDGs時代の食べ方』『捨てないパン屋の挑戦』など著書多数。
お天気カレンダー 冬至
 2024年12月21日は、二十四節気の冬至です。一年の中で太陽の高度が最も低い日で、昼間の時間が最も短くなる日です。弱々しい太陽の光に、寒さもいっそう厳しく感じる頃になります。冬至には、黄色く熟し、旬を迎えたユズを浮かべた「ゆず湯」に入る習慣がありますね。ぜひ、ゆず湯に入って、冷えた体を温めたいところです。
2024年12月21日は、二十四節気の冬至です。一年の中で太陽の高度が最も低い日で、昼間の時間が最も短くなる日です。弱々しい太陽の光に、寒さもいっそう厳しく感じる頃になります。冬至には、黄色く熟し、旬を迎えたユズを浮かべた「ゆず湯」に入る習慣がありますね。ぜひ、ゆず湯に入って、冷えた体を温めたいところです。
冬至の日に行うこととして、ゆず湯に入る他、「ん」の付く食べ物を食べると良いといわれます。ニンジン、ダイコン、レンコン、カボチャなど。ん? カボチャには「ん」がついていません。でも、カボチャは「南京(なんきん)」ともいわれるので、冬至に食べると縁起が良いといわれています。カボチャには風邪を予防する効果もあり、この時期に食べるにはうってつけです。皆さんは、冬至には何をしますか? 私は毎年冬至にはゆず湯に入ります。これだけは「ゆず」れません。
気象予報士・防災士 檜山 靖洋(ひやま やすひろ) 1973年横浜市生まれ。
明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。
1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。 2005年からNHKの気象キャスターに。
朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。